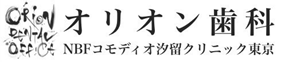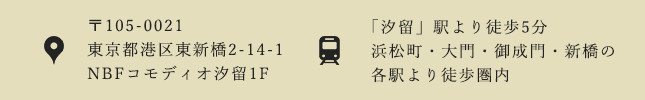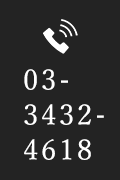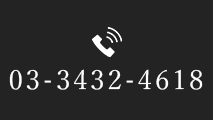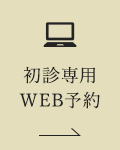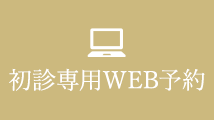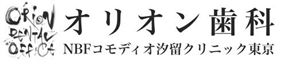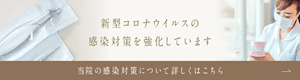1. 歯がグラグラする原因とは?考えられる3つの理由
① 歯周病による歯槽骨の吸収:歯を支える骨が減少し、歯が動揺する
歯周病は日本人の成人の多くが抱える疾患であり、歯を失う最大の原因とされています。歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨が溶け、歯が支えを失い、動揺しやすくなります。
- 初期段階では歯ぐきの腫れや出血など軽微な症状が見られる。
- 進行すると歯ぐきが退縮し、最終的には歯が抜け落ちる可能性がある。
- 歯周病菌が血流に乗って全身の健康にも影響を及ぼすことがある。
定期的な歯科検診とクリーニングを行い、早期に発見・治療することが重要です。
② 歯ぎしり・噛みしめの影響:過剰な負荷が歯にかかり、ダメージが蓄積
歯ぎしりや強い噛みしめは、歯に大きなストレスを与え、長期間続くことで歯がぐらつく原因になります。特に、就寝中に無意識に歯ぎしりをしている人は多く、朝起きたときに顎の違和感や歯の痛みを感じることがあります。
- 過度な力が歯根や歯槽骨に影響を与え、歯の動揺を引き起こす。
- 歯の表面がすり減ったり、歯がひび割れたりするリスクが高まる。
歯ぎしりが疑われる場合は、ナイトガード(マウスピース)の装着が有効で、歯科医院で自分に合ったものを作成してもらうことで、歯への負担を軽減できます。また、ストレスが歯ぎしりの原因になることもあるため、リラックスする習慣を持つことも予防につながります。
③ 歯根破折(歯の根のヒビや割れ):見えない部分でダメージが進行している可能性
歯根破折とは、歯の根にヒビが入ったり、割れたりする状態のことを指します。これは、強い噛みしめや歯ぎしり、過去の根管治療による影響で起こることが多く、肉眼では確認しにくいため、発見が遅れがちです。
- 歯がぐらつくだけでなく、噛むと痛みを感じたり、歯ぐきが腫れたりすることがある。
- 特に、根管治療を受けた歯は感覚が鈍くなっており、破折に気づきにくい。
レントゲンやCT検査を行うことで診断が可能になり、適切な治療法を選択することができます。軽度であれば接着治療や補強が可能な場合もありますが、進行が進むと抜歯が必要になるケースもあるため、違和感を感じたら早めの診察を受けることが重要です。
2. 歯根破折とは?歯の根が割れるとどうなるのか

① なぜ歯の根が折れるのか?(噛み合わせの強い負担、過去の治療の影響)
歯根破折は、歯の根がヒビ割れたり、完全に折れたりする現象で、多くの場合、噛み合わせの強い負担や過去の治療の影響によって引き起こされます。
- 根管治療を受けた歯は神経がなく、歯の強度が低下しているため、噛む力や外的ストレスに弱くなっている。
- 強い噛みしめや歯ぎしりを長期間続けると、歯にひびが入りやすくなり、歯根破折につながる。
- 事故やスポーツ中の衝撃が原因で、急激に歯の根が折れるケースもある。
特に、奥歯は噛む力が強くかかるため、歯根破折が起こりやすい傾向にあります。早期発見が重要です。
② 初期は気づきにくいが、進行すると痛みや腫れが出る
歯根破折は初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気づきにくいのが特徴です。しかし、破折が進行すると、次のような症状が現れます。
- 噛むと違和感がある。
- 噛んだときに軽い痛みを感じる。
- 歯ぐきの腫れや膿が出ることがある。
- 歯ぐきにフィステル(膿の出口)ができる。
- 破折部分が大きくなると、歯がグラグラ動く。
破折した部分から細菌が侵入すると、感染が広がり、炎症が悪化します。特に、周囲の骨にまで影響が及ぶと、抜歯が避けられなくなる可能性があります。
③ 破折したまま放置すると、歯を失うリスクが高まる
歯根破折を放置すると、次のようなリスクが生じます。
- 感染が進行し、歯ぐきの炎症が悪化する。
- 歯を支えている骨(歯槽骨)が吸収され、歯の動揺が進む。
- 破折部分が大きくなると、最終的に抜歯が必要になる。
- 歯槽骨の吸収が進むと、インプラントなどの治療の選択肢が制限される可能性がある。
早期発見・早期治療が不可欠です。歯科医院でレントゲンやCT検査を受け、詳細な診断を行うことで、適切な治療法を選択できる可能性が高まります。
3. 放置すると危険!歯根破折による3つのリスク

① 細菌感染が進み、歯ぐきが腫れてしまう
歯根破折が発生すると、破折部分から細菌が侵入しやすくなります。その結果、歯根周囲で細菌が繁殖し、炎症が起こりやすくなります。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、「少し違和感がある」程度の状態でも放置されがちです。しかし、時間の経過とともに歯ぐきの腫れがひどくなり、痛みや圧迫感を感じるようになります。
- 感染が進むと、膿がたまりフィステル(膿の出口)ができることもある。
- 炎症が骨にまで及ぶと、顎の骨が溶けてしまうことがある。
- 顎の骨が失われると、インプラントやブリッジの治療が困難になる。
このようなリスクを避けるためには、違和感を感じた時点で早めに歯科医院を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
② 周囲の歯や骨にも影響を及ぼし、さらに抜歯が必要になる可能性
破折した歯を放置すると、炎症が広がり、隣接する健康な歯にも影響を及ぼします。特に、細菌感染が歯槽骨にまで及ぶと、骨が溶けてしまい、歯を支える力が弱くなります。
- 骨が失われると、破折した歯だけでなく、周囲の歯もグラグラするようになる。
- 長期間炎症が続くと、歯周病を引き起こし、さらに多くの歯を失うリスクが高まる。
- 最悪の場合、総入れ歯やインプラント治療が必要になる可能性がある。
このようなリスクを避けるためには、歯科医院での早期診断と適切な治療が不可欠です。
③ 抜歯後の治療選択肢が限られる(インプラントやブリッジが困難になることも)
破折した歯を抜歯した場合、インプラントやブリッジ、義歯などの治療選択肢があります。しかし、長期間放置し炎症が進行すると、顎の骨の吸収が進み、インプラント治療が難しくなることがあります。
- インプラントを埋め込むための骨量が不足し、骨移植が必要になることも。
- ブリッジを選択すると、隣接する歯に負担がかかり、他の歯の寿命を縮めるリスクがある。
- 炎症が長引くと、抜歯後の治療の選択肢が制限される可能性がある。
抜歯を避けるためには、早期に適切な治療を受け、できるだけ歯を保存することが重要です。歯に違和感を感じたら、すぐに歯科医院で相談しましょう。
4. どんな症状がある?歯根破折のサインを見逃さないで

① 噛んだときの違和感や痛みが続く
歯根破折の初期段階では、強い痛みを感じることは少ないものの、噛んだときに違和感が続くことが特徴です。特に、食事中に「何か硬いものを噛んだような感覚」があったり、特定の歯だけが噛みづらいと感じる場合は、歯根破折の可能性があります。
- 破折が進行すると、噛むたびに痛みが増す。
- 硬いものだけでなく、柔らかい食べ物でも違和感を覚えるようになる。
- 痛みが断続的に続く場合は、破折が深刻化している可能性が高い。
違和感を感じたら、歯科医院でレントゲンやCT検査を受けることで、表面からは見えない破折を早期に発見できます。早めの受診が重要です。
② 歯ぐきが腫れる、出血や膿が出る
歯根破折が原因で細菌感染が進むと、歯ぐきに腫れが生じます。特に、歯ぐきの一部分だけがポコッと膨らんだようになった場合は、フィステル(膿の出口)が形成されている可能性があります。
- 歯磨きの際に血が出やすくなるのも炎症のサイン。
- 膿が出る場合は、感染が進行している可能性が高い。
- 炎症が歯槽骨に広がると、周囲の組織がダメージを受けやすくなる。
このような症状を放置すると、感染が広がり、抜歯が必要になるリスクが高まります。歯ぐきの腫れが繰り返し起こる場合は、自然には治らないため、適切な治療を早期に受けることが重要です。
③ 冷たいものや温かいものがしみる、歯のぐらつきが増している
歯根破折が進行すると、歯がぐらつくことが増えます。特に、歯を触るとわずかに動くような感覚がある場合は、歯根のダメージが進行している可能性が高いです。また、冷たいものや温かいものがしみる症状も、歯根のトラブルによって引き起こされることがあります。
- 歯のぐらつきが進むと、噛み合わせの問題が生じることがある。
- 他の歯に負担がかかり、周囲の歯まで影響を受ける可能性がある。
- 歯ぐきが下がり、歯が長く見えることも歯根破折のサイン。
ぐらつきの進行は、破折が深刻化しているサインである可能性が高く、早期の介入が求められます。歯ぐきの変化にも注意し、違和感を覚えたら早めの検査を受けましょう。
5. 破折した歯は必ず抜歯?治療の選択肢を知ろう

① 軽度の破折なら接着治療で保存できる可能性も
歯根破折と診断されても、必ずしも抜歯が必要になるわけではありません。破折の程度が軽度であれば、接着治療によって歯を保存できる可能性があります。
接着治療とは?
特殊な歯科用接着剤を用いて破折部分を固定し、歯を一体化させる治療法です。特に、破折が歯根の上部に限られている場合や、破折線が浅い場合には有効とされています。
- 歯の状態によっては、接着治療が成功する可能性がある。
- 治療後もナイトガード(マウスピース)を装着し、再破折を防ぐ。
- 咬み合わせの調整や、定期的なメンテナンスが必要。
ただし、接着治療が可能かどうかは破折の位置や範囲によるため、歯科医師の診断を受けることが重要です。
② 歯ぐきの奥まで割れている場合は、抜歯が必要になることが多い
破折が歯ぐきの奥深くまで達している場合は、保存が困難となり、抜歯が必要になるケースが多くなります。
- 歯根の深い部分に亀裂が入ると、細菌が侵入しやすくなる。
- 炎症が進行すると、歯周組織や周囲の歯にも悪影響を及ぼす。
- 慢性的な感染が続くと、歯槽骨が溶ける可能性がある。
破折した歯を放置すると、口腔環境の悪化を招くため、早めに治療を受けることが重要です。抜歯が必要な場合でも、適切な治療計画を立てることで、咀嚼機能や見た目を維持できます。
③ 早期発見がカギ!できるだけ歯を残すための治療法とは
歯根破折の治療で最も重要なのは、早期発見と適切な治療の選択です。破折が発生した直後であれば、保存治療の可能性が高くなります。そのため、歯に違和感を感じたら、放置せずに早めに歯科医院を受診することが大切です。
保存の可能性がある治療法:
- 歯根端切除術:感染部分を切除し、歯を保存する治療法。
- MTAセメントによる修復:生体親和性の高い材料で破折部分を補強。
- 再接着治療:条件が良ければ、破折部分を特殊な接着剤で固定可能。
近年の治療技術の進歩により、従来なら抜歯が必要だったケースでも、歯を残せる可能性が高まっています。歯科医師と相談し、自分に最適な治療方法を選択することが重要です。
6. 歯根破折が疑われたら、まず受けるべき検査とは?
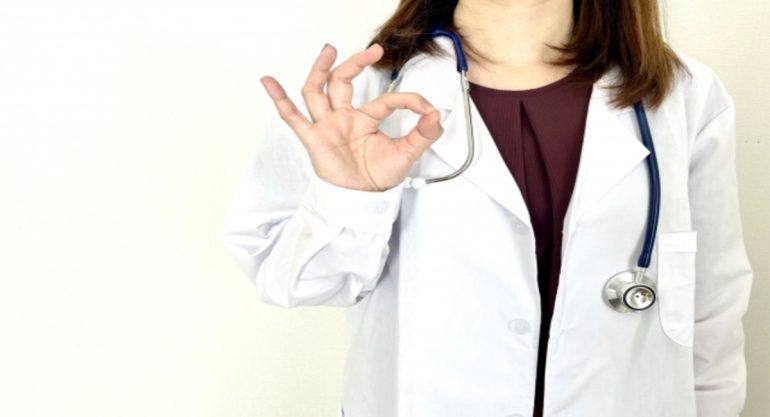
① レントゲン・CT検査で見えない部分を確認
歯根破折は肉眼では確認が難しいため、レントゲンやCT検査を行い、破折の位置や状態を詳しく調べる必要があります。
- レントゲン検査:破折の大まかな位置を把握するのに有効。
- CT検査:歯を立体的に映し出し、細かいヒビや破折線をより精密に診断できる。
早期発見が重要!
歯根破折の初期段階では自覚症状が少ないため、「痛みがないから大丈夫」と思わず、違和感を感じた時点で検査を受けることが大切です。放置すると治療の選択肢が狭まり、抜歯のリスクが高まることもあります。
② 肉眼では見えないヒビや破折線を発見できる
歯根破折の診断には、以下の特殊な検査が用いられます:
- 咬合テスト:噛んだ際の痛みの有無や強さを確認し、破折の可能性を判断。
- 歯冠除去テスト:詰め物や被せ物を外して、破折の状態を直接観察。
- 染色テスト:破折部分を染色し、ヒビの状態を明確化。
デジタル技術による診断の進化
最近では、口腔内スキャナーを使って3Dモデルを作成し、より精密に破折を確認する技術も進化しています。
③ 早めの診断で治療の選択肢を増やすことができる
早期診断のメリット:
- 破折の進行が浅い場合、接着治療や部分修復が可能。
- 放置すると炎症が進み、最終的に抜歯が必要になるリスクが高まる。
- ナイトガードの使用や、噛み合わせの調整で破折の悪化を防ぐことができる。
「そのうち治るだろう」は危険!
痛みが強くなる前に歯科医院を受診し、精密検査を受けることが重要です。
④ 歯根破折の診断後にすべきこと
診断後は、歯科医師と相談し、最適な治療方針を決定します。
治療の選択肢:
- 接着治療:破折が軽度の場合に有効。
- 歯根端切除術:感染部分を切除し、歯を保存する手術。
- 歯冠延長術:破折が歯ぐきの奥まで達している場合、歯を長くして修復する。
- 抜歯:破折が重度の場合、やむを得ず選択。
治療後のメンテナンスも重要!
破折の原因を特定し、再発を防ぐためのケアを徹底することが、長期的な口腔健康の維持につながります。
7. 予防が大切!歯根破折を防ぐためにできること

① 強く噛みしめる癖があるならナイトガードの活用を
日常的な噛みしめや歯ぎしりは、歯根破折の大きな原因となります。特に、就寝中の歯ぎしりは自覚しづらく、知らない間に歯に強い負担をかけてしまいます。長期間続くと、歯根に小さなひびが入り、歯根破折のリスクが高まります。
ナイトガード(マウスピース)を装着することで、噛み合わせの圧力を分散し、歯への負担を軽減できます。
- 歯科医院でオーダーメイドのナイトガードを作成することで、市販品よりフィット感が良く、効果的に歯を保護できる。
- 特に奥歯に負担がかかりやすい方や歯ぎしりが習慣化している方には推奨される。
- ナイトガードを使うことで、歯だけでなく顎関節への負担も軽減できる。
ナイトガードの使用を検討し、歯科医師と相談しながら適切な対策を講じましょう。
② 歯ぎしり対策をすることで、歯の負担を軽減
歯ぎしりの予防には、ナイトガードの使用以外にも、生活習慣の見直しが効果的です。ストレスが歯ぎしりの原因となることも多いため、リラックスする習慣を取り入れましょう。
- 寝る前に深呼吸やストレッチを行い、リラックスする時間を作る。
- カフェインやアルコールの摂取を控える(興奮作用が歯ぎしりを誘発)。
- 寝具や枕を調整し、良質な睡眠環境を整える。
日中の噛みしめ癖にも注意が必要です。
無意識に歯を食いしばる癖がある方は、定期的に顎の筋肉をほぐす意識を持ちましょう。
- 「上下の歯を離す」ことを意識する。
- ガムを噛む際は、左右均等に噛むように心がける。
噛みしめが続くと、歯だけでなく顎関節にも影響を与えます。口の健康を維持するためにも、適切な対策を講じましょう。
③ 定期的なメンテナンスで、歯の状態をチェックしてもらう
歯根破折は予防が最も重要!
そのためには、定期的な歯科検診を受けることが欠かせません。歯科医院でのメンテナンスを受けることで、破折リスクの高い歯を事前に確認し、適切な処置を施すことができます。
定期検診でチェックすべきポイント:
- 噛み合わせのバランス:特定の歯に過度な負担がかかっていないかを診断。
- 歯周病の進行状況:歯ぐきが健康かどうかをチェック。
- 歯のひび割れ:破折のリスクがある歯を早期発見。
定期的なプロフェッショナルクリーニング(PMTC)を受けることで、歯の表面を滑らかに保ち、細菌の蓄積を防ぐことも可能です。
また、歯周病やむし歯のリスクを軽減することで、歯根破折の発生を抑えることができます。
④ まとめ:歯根破折予防のために今日からできること
- ナイトガードを活用し、噛みしめや歯ぎしりの負担を軽減する。
- 生活習慣を見直し、リラックスできる環境を整える。
- 定期的な歯科検診を受け、破折リスクのある歯を早期発見する。
- PMTC(プロフェッショナルクリーニング)で歯の健康を維持する。
歯根破折は予防が最も重要です。
日頃のセルフケアと歯科医院での定期検診を組み合わせ、歯を健康に保ちましょう!
8. すでにグラグラしている歯をそのままにするとどうなる?

① 周囲の歯にも負担がかかり、次々に影響が出る
歯がグラグラしている状態を放置すると、周囲の健康な歯にも悪影響を及ぼします。特に、噛み合わせのバランスが崩れることで、隣接する歯や反対側の歯に過度な負担がかかり、結果的に健康な歯までダメージを受けやすくなります。
- 片側の歯が弱ると、反対側で噛む習慣がつき、反対側の歯や顎関節に負担がかかる。
- グラついた歯があると噛みにくくなり、食事のバランスが崩れ、咀嚼機能が低下する。
- 咀嚼機能の低下により、消化不良や胃腸への負担が増加。
グラグラした歯を放置することで、周囲の歯や全身の健康にも影響が出るため、早めの治療が重要です。
② 噛み合わせが悪くなり、顎関節症のリスクが高まる
歯がグラつくことで噛み合わせがズレると、顎関節への負担が増し、顎関節症を引き起こす可能性があります。
顎関節症の主な症状:
- 顎がカクカク鳴る、開閉時に違和感がある。
- 顎の痛みやこわばりを感じる。
- 頭痛や肩こりが頻繁に起こる。
- 口を大きく開けられなくなる。
顎関節症が進行すると、食事や会話に支障をきたすため、グラつく歯がある場合は、早めに歯科医院で診察を受けましょう。
③ 最終的に抜歯が必要になり、治療の選択肢が限られる
グラグラしている歯を長期間放置すると、最終的に抜歯が必要になることが多くなります。歯が抜けると、噛み合わせのバランスが崩れ、残っている歯への負担が増加します。
- 歯が抜けたまま放置すると、隣接する歯が傾き、噛み合わせが悪化する。
- 歯槽骨(歯を支える骨)が吸収され、インプラントが困難になることがある。
- 治療選択肢として、インプラント・ブリッジ・入れ歯があるが、放置すると適応が難しくなる。
抜歯が必要になる前に、歯科医院で適切な治療を受けることが重要です。 早めに相談し、最適な治療計画を立てましょう。
④ まとめ:グラグラした歯を放置しないために
- 噛み合わせが悪くなる前に、歯科医院で診察を受ける。
- 周囲の歯への影響を防ぐために、早めに治療を開始する。
- 抜歯が必要になる前に、歯周病治療や補綴治療を検討する。
グラつく歯を放置すると、噛み合わせの悪化や周囲の歯の負担増加につながります。
早めの診察と適切な治療で、歯を守りましょう!
9. 歯根破折のリスクが高い人とは?

① 過去に根管治療を受けた歯が多い人(治療済みの歯は脆くなりやすい)
歯根破折のリスクが特に高いのは、過去に根管治療を受けた歯が多い人です。根管治療を受けた歯は、神経が除去されているため血流がなくなり、歯の強度が低下します。その結果、噛む力や衝撃に対して脆くなり、ひびが入りやすくなります。
- 根管治療後の歯は神経がないため、衝撃に弱い。
- 詰め物や被せ物で補強されていても、歯の内部が劣化しているため破折しやすい。
- 特に奥歯は噛む力が強くかかるため、破折リスクが高い。
対策: ナイトガードの使用や、定期的な検診で歯の状態をチェックすることが大切です。
② 強い噛みしめや歯ぎしりの癖がある人(過度な力が歯にダメージを与える)
歯根破折のリスクを高めるもう一つの要因は、無意識の噛みしめや歯ぎしりです。 特に就寝中の歯ぎしりは、自覚がないまま歯に強い力をかけるため、気づかないうちにダメージが蓄積します。
- 強い力がかかると歯のエナメル質にひびが入る。
- 治療済みの歯や神経がない歯は、特に破折のリスクが高い。
- 長期間続くと、破折につながる可能性がある。
予防策:
- ナイトガード(マウスピース)を装着し、歯への負担を軽減。
- ストレスを軽減するリラックス習慣(例:寝る前のストレッチや瞑想)。
- 噛み合わせの調整で特定の歯に負担がかからないようにする。
③ スポーツや事故で歯に衝撃を受けたことがある人(小さなヒビが徐々に悪化する可能性)
スポーツや事故で歯に強い衝撃を受けた経験がある人も、歯根破折のリスクが高いグループに入ります。衝撃によって歯に微細なヒビが入ると、すぐには症状が現れなくても、時間の経過とともに亀裂が広がり、最終的に破折につながることがあります。
- コンタクトスポーツ(ラグビー、バスケットボール、ボクシングなど)をしている人は注意が必要。
- 転倒や事故で歯をぶつけたことがある人も、破折のリスクが高い。
- 目立ったダメージがなくても、レントゲンやCT検査で歯根の状態を確認することが重要。
予防策:
- スポーツをする際には、マウスガードを装着して歯を保護。
- 事故後は、早めに歯科検診を受ける。
- 強い衝撃を受けた後、異変がなくても定期的に歯の状態をチェック。
④ まとめ:歯根破折のリスクが高い人がすべきこと
- 根管治療後の歯は特に注意し、噛み合わせを定期的にチェック。
- 歯ぎしり・噛みしめの癖がある人は、ナイトガードを活用。
- スポーツや事故で衝撃を受けた人は、歯科医院で検査を受ける。
歯根破折は早期発見と適切な予防がカギとなります。
気になる症状があれば、すぐに歯科医院へ相談しましょう!
10. 「歯がグラつく」と感じたら、すぐに歯科医院へ!

① 放置せず、早めに歯科医院で診察を受けることが大切
歯がグラグラする感覚がある場合、それは歯や歯ぐきに何らかの問題が発生しているサインです。特に、歯根破折や進行した歯周病が原因の場合、放置すると症状が悪化し、最終的に抜歯が必要になる可能性が高まります。
早期発見で歯を残せる可能性が格段に高くなるため、違和感を感じたら早めに歯科医院を受診しましょう。
- 歯科医院ではレントゲンやCT検査を活用し、歯の根や歯槽骨の状態を正確に診断。
- 歯根破折は早期発見が重要で、治療が遅れると周囲の歯や骨にも影響を及ぼす。
- 「痛みがないから大丈夫」と自己判断せず、歯科医師の診察を受けることが口腔内の健康を守る第一歩。
② 歯を残せる可能性を高めるためにも、早期発見が重要
歯がグラつく原因はさまざまですが、早期に治療を開始すれば、抜歯を避けることができるケースも多くあります。
| 原因 | 治療方法 |
|---|---|
| 軽度の歯根破折 | 接着治療や補強で保存可能 |
| 歯周病による歯の動揺 | 専門的なクリーニングや歯周病治療で改善 |
| 噛み合わせの不調 | 調整やナイトガードの使用で負担を軽減 |
放置せず、できるだけ早く歯科医院で診察を受けることが重要です。
③ まずは検査を受け、自分の歯の状態を正しく知ることから始めよう
歯のグラつきが気になったら、まずは検査を受けることが大切です。歯科医院で受けられる主な検査には以下のようなものがあります。
- レントゲン検査:歯根の状態や骨の吸収を確認する
- CT検査:歯根破折や歯槽骨の詳細な状態を立体的に診断
- 歯周ポケット測定:歯周病の進行度を調べる
- 噛み合わせ診断:過度な負担がかかっている歯がないかをチェック
正確な診断が適切な治療の第一歩であり、将来的に健康な歯を維持するための重要なポイントです。
④ まとめ:歯がグラつくと感じたら、今すぐ行動を!
- 歯科医院で検査を受け、歯の状態を正しく知る。
- 早期に治療を開始することで、歯を残せる可能性を高める。
- 治療後のメンテナンスを徹底し、再発を防ぐ。
定期的なメンテナンスと適切な治療を受けることで、健康な歯を長く維持できます。
「歯がグラグラする」と感じたら、すぐに歯科医院へ相談しましょう!
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事