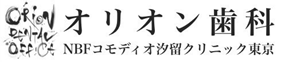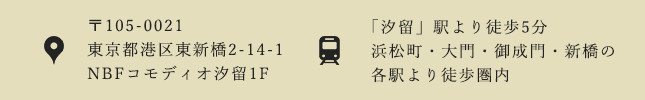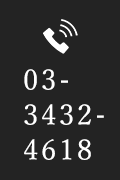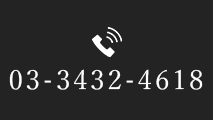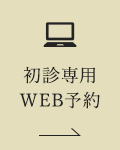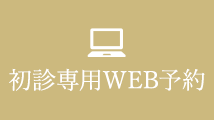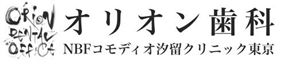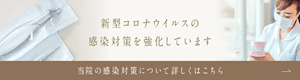歯の位置がズレる原因とは?知らないうちに起こる「転位」と「陥入」

歯が正常な位置から移動するメカニズム
歯は、顎の骨や歯ぐき、周囲の歯とのバランスによって適切な位置を保っています。しかし、何らかの要因によってこのバランスが崩れると、歯が本来の位置からズレることがあります。
- 転位:歯が通常の生える位置から外れてしまう現象で、歯列から外れたり、ねじれたりすることがあります。
- 陥入:歯が顎の骨の内部にめり込んでしまい、正常な高さに出てこない状態を指します。
歯が移動する要因として、顎の成長や噛み合わせの変化が大きく影響します。成長期の子どもでは、顎の発達に伴い歯の位置が変化し、スペースが不足すると歯のズレが生じることがあります。また、成人になってからも、歯ぎしりや食いしばりが原因で特定の歯に負担がかかり、少しずつ移動してしまうことがあります。
噛み合わせの乱れや外傷による影響
歯の位置がズレる大きな要因の一つが、噛み合わせの乱れです。噛み合わせが正常でない場合、特定の歯に過剰な力がかかり、歯が移動しやすくなります。
- 歯ぎしりや食いしばりによる圧力で歯が徐々にズレる。
- 片側だけで食べる癖があると、使わない側の歯が支えを失い、傾いたり浮き上がったりする。
また、外傷も歯のズレの原因になります。スポーツや事故で強い衝撃を受けると、歯が転位や陥入を引き起こすことがあります。特に前歯は外部からの影響を受けやすく、衝撃を受けた際に内側や外側に移動することがあります。
成長期や加齢による歯の動きの変化
歯の位置のズレは、成長期や加齢によっても起こります。
成長期の影響
- 顎の発達に伴い歯が自然に動く。
- スペース不足により「叢生(そうせい)」が発生し、歯が重なり合う。
- 歯並びが乱れることで、清掃がしにくくなり虫歯や歯周病のリスクが上昇。
加齢の影響
- 歯ぐきが痩せ、顎の骨が減少すると歯が支えを失い移動しやすくなる。
- 歯を失ったまま放置すると、周囲の歯が空いたスペースに移動し噛み合わせが乱れる。
- 歯の位置がズレると、顔の形にも影響し、口元がへこんだり顔の非対称が目立つことも。
加齢による歯の移動を防ぐためには、定期的な歯科検診を受け、歯ぐきや顎の骨の状態をチェックすることが重要です。また、歯ぎしりや食いしばりが原因で歯が移動している場合は、マウスピースを活用することで負担を軽減し、歯のズレを防ぐことができます。
歯がズレたまま放置するとどうなる?口腔内のトラブル

ズレた歯が引き起こす噛み合わせの異常
歯の位置がズレたまま放置すると、噛み合わせが乱れ、口腔機能全体に影響を及ぼす可能性があります。正常な歯並びでは、上下の歯が適切に接触し、バランスの取れた咀嚼が行われます。しかし、歯が転位や陥入を起こしていると、一部の歯に過度な負担がかかり、噛み合わせが崩れてしまうことがあります。
- 食事時の噛みにくさ:歯のズレによって、上下の歯が正しく噛み合わなくなり、食事がしにくくなる。
- 顎関節への影響:噛み合わせの不均衡が顎関節に負担をかけ、顎関節症を引き起こす可能性がある。
- 歯ぎしり・食いしばりの悪化:ズレた歯の位置を補おうとする体の反応で、無意識に歯ぎしりや食いしばりが発生しやすくなる。
- 歯のすり減りや破損:噛み合わせの乱れによって、一部の歯が過剰にすり減ったり、詰め物や被せ物が取れやすくなったりする。
特に、歯がズレることで無意識の食いしばりが強くなり、さらに歯が動いてしまうという悪循環が生じる可能性があります。そのため、早めの対応が重要です。
歯磨きが難しくなり、虫歯や歯周病のリスクが上がる
歯の位置がズレると、歯と歯の間の隙間が広がったり、逆に歯が重なったりすることで、ブラッシングが難しくなります。これにより、歯垢や食べかすが溜まりやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
- 歯が重なり合っている場合:歯ブラシの毛先が届きにくく、清掃が不十分になりやすい。
- 歯の隙間が広がる場合:食べかすが詰まりやすくなり、細菌が繁殖しやすくなる。
- 歯周病の進行リスク:歯垢や歯石が蓄積しやすくなり、歯周ポケットが深くなってしまう。
- 知覚過敏の発生:歯ぐきが下がり、歯の根元が露出することで、冷たいものや熱いものがしみるようになる。
また、陥入した歯(顎の骨の中にめり込んでしまった歯)の場合、その周囲に細菌が繁殖しやすく、歯ぐきが炎症を起こしやすくなります。進行すると、歯を支える骨にダメージを与え、歯がグラグラする原因になることもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、定期的な歯科検診を受け、歯のズレが進行しないように管理することが重要です。早期に対処することで、虫歯や歯周病のリスクを軽減し、長期的に健康な歯を維持することが可能になります。
歯や歯ぐきに過度な負担がかかり、痛みや違和感が生じる
歯がズレたままの状態では、特定の歯に過度な負担がかかり、痛みや違和感を引き起こすことがあります。正しい噛み合わせでは、全体の歯が均等に力を分散しますが、歯の位置がズレていると、特定の歯だけに負担が集中してしまい、痛みを感じやすくなります。
- 歯の痛み:ズレた歯に過度な力がかかることで、噛むと痛みを感じることがある。
- 歯ぐきの炎症:ズレた歯が歯ぐきに圧力をかけ、腫れや歯ぐきの退縮を引き起こす。
- 知覚過敏の発生:歯ぐきが下がることで、歯の神経が露出し、冷たいものや熱いものがしみる。
- 神経への影響:歯の根に強い圧力がかかると、神経が圧迫され、ズキズキとした痛みを感じることがある。
特に、歯の根に負担がかかると、神経が炎症を起こし、歯の神経を抜く治療(根管治療)が必要になることもあります。そのため、歯のズレによる痛みや違和感が続く場合は、早めに歯科医院で相談することが大切です。
転位や陥入による顎関節への影響

噛み合わせが悪化し、顎関節症のリスクが高まる
歯の位置がズレると、噛み合わせのバランスが崩れ、顎関節症(がくかんせつしょう)を引き起こすリスクが高まります。顎関節症は、顎の関節や周囲の筋肉に過度な負担がかかることで、顎の動きに異常が生じる症状を指します。特に、歯が転位や陥入を起こしている場合、上下の歯の接触が不均一になり、顎の動きがスムーズに行えなくなることがあります。
- 顎の筋肉の緊張:噛み合わせが乱れることで、顎の筋肉が常に緊張し、食事時に顎が疲れやすくなる。
- 口の開閉がスムーズにできない:歯のズレによって、口を開くとカクカクと音がする、開閉がスムーズにいかないといった症状が現れる。
- 片側噛みの習慣がつく:無意識のうちに片側ばかりで噛むようになり、さらに噛み合わせが悪化する。
- 慢性的な頭痛・肩こりの原因に:噛み合わせのズレが顎関節に影響を与え、全身の筋肉に負担をかける。
特に、歯の位置がズレていると、顎が本来の正しい位置に戻ろうとする力が働くため、寝ている間に歯ぎしりや食いしばりが強くなることがあります。これにより、さらに歯が移動しやすくなり、顎関節にかかる負担が増加する悪循環に陥る可能性が高くなります。
顎の筋肉や関節に負担がかかり、口が開きにくくなることも
歯の位置のズレが進行すると、顎の筋肉や関節に負担がかかり、口の開閉がスムーズに行えなくなることがあります。これは、顎の関節を支える筋肉に不均等な力がかかるため、筋肉が緊張してしまうことが原因です。
- 顎関節の動きに異常が生じる:噛み合わせがズレていると、関節の可動域が狭くなり、開口制限が起こることがある。
- 初期症状:「口を開けるときに引っかかる感じがする」「開閉時にカクカクと音がする」といった軽い症状が現れる。
- 進行すると:痛みを伴い、口を大きく開けることが困難になることがある。
- 顔のバランスの変化:顎の筋肉に負担がかかると、片側の筋肉が過度に発達し、顔の非対称が目立ちやすくなる。
このような状態が続くと、顎関節や筋肉の慢性的な痛みにつながり、頭痛や肩こり、首の痛みを引き起こすことがあります。特に、長時間デスクワークをする方や、スマートフォンを長時間使用する方は、姿勢の乱れが顎関節に影響を与えやすいため、注意が必要です。
放置すると顎関節の変形や慢性的な痛みにつながる可能性
歯の位置のズレが長期間放置されると、顎関節に慢性的な負担がかかり、関節の形が変形する可能性があります。これは、顎関節の内部にある軟骨や関節円板がすり減ったり、ズレたりすることで発生します。
- 顎関節の変形が進むと:口の開閉時に痛みが生じる、関節の可動域が狭くなる。
- 炎症が慢性化すると:顎関節自体が変形し、骨の摩耗が進む。
- 食事の影響:噛むと痛みを感じるようになり、咀嚼機能が低下する。
顎関節の変形が進行すると、歯の治療だけでは改善が難しくなり、専門的な顎関節治療や手術が必要になることもあります。そのため、歯の位置がズレた状態を放置せず、早めに歯科医院で診察を受け、適切な治療を行うことが重要です。
顎関節の変形を予防するためにできること
- 定期的な噛み合わせのチェックを受ける:歯のズレが進行しないように管理する。
- ナイトガード(マウスピース)の活用:歯ぎしりや食いしばりが強い場合、ナイトガードを使用することで筋肉の緊張を和らげ、顎関節への負担を軽減できる。
- 正しい姿勢を意識する:デスクワークやスマートフォンの使用時に、猫背にならないよう気をつける。
- 顎のストレッチやマッサージを取り入れる:顎の筋肉の緊張をほぐし、柔軟性を維持する。
顔の歪みは歯のズレが原因?見た目にも影響を与える歯並びの変化

歯の位置がズレることで顔の非対称が目立つようになる
歯の位置のズレは、見た目の問題にも大きな影響を与えます。特に、歯が転位や陥入を起こしている場合、顔全体のバランスが崩れ、左右非対称の歪みが目立つようになることがあります。これは、歯並びが変化することで、噛み合わせや顎の位置がズレるためです。
- 奥歯の倒れ込み: 片側の奥歯が内側に倒れていると、噛み合わせが低くなり、顎がそちらに傾く。
- 前歯の傾き: 前歯が斜めに傾いていると、口元の歪みが強調され、左右の高さが違って見える。
- 筋肉の偏り: 歯の位置がズレることで、片側の顔の筋肉が発達し、反対側が衰えることでフェイスラインが崩れる。
これらの問題は、噛み合わせのバランスを整えることで改善できるケースが多いため、早めに歯科医院で診察を受け、必要に応じて矯正治療を検討することが重要です。
頬や口元の筋肉に左右差が生じ、フェイスラインが崩れる
歯の位置がズレると、噛む力のかかり方が変化し、顔の筋肉にも影響を及ぼします。左右の噛む力が均等でないと、筋肉のバランスが崩れ、フェイスラインが歪む原因になります。
- 片側噛みの影響: 片側ばかりで噛むと、その側の筋肉が発達し、反対側の筋肉が衰え、顔が非対称になる。
- 発音への影響: 歯の傾きやねじれがあると、発音時の口の動きが歪み、口角の高さに左右差が生じる。
- 表情の不自然さ: 顎の位置のズレが原因で、顔の片側がこわばり、表情が不自然になる。
このような変化を防ぐためには、噛み合わせを整え、左右均等に噛む習慣をつけることが大切です。歯科医院での矯正治療や噛み合わせの調整を受けることで、顔のバランスを整える手助けができる場合もあるため、気になる症状がある場合は専門医に相談しましょう。
長期間放置すると、顔のバランスが変わり、老けた印象に
歯の位置のズレを長期間放置すると、顔の骨格にも影響を与えることがあります。歯が正しく並んでいる場合、顎の骨が適切に支えられ、若々しいフェイスラインを維持することができます。しかし、歯が転位や陥入を起こしていると、顎の骨のバランスが崩れ、顔の形が変化する原因となることがあります。
- 頬のたるみ: 奥歯の位置がズレて噛み合わせが低くなると、頬の筋肉が支えを失い、口元にたるみが生じる。
- ほうれい線が深くなる: 顎のズレによって皮膚が引っ張られ、シワが目立ちやすくなる。
- 唇の形の変化: 前歯の傾きによって口元が突出したり、逆にへこんだりすることで顔の印象が変わる。
- 二重あごの原因: 噛み合わせの乱れが顎の筋肉に負担をかけ、フェイスラインの崩れにつながる。
このような問題を防ぐためには、歯の位置のズレを早めに矯正し、適切な噛み合わせを維持することが大切です。矯正治療や噛み合わせの調整を行うことで、顔のバランスを整え、若々しい印象を維持することができます。
歯がズレる主な原因とは?日常生活での習慣が影響

歯ぎしりや食いしばりが歯の位置を変えてしまう
歯ぎしりや食いしばりの習慣は、歯に強い負荷をかけるため、歯の位置を少しずつ移動させる原因になります。特に、就寝中の無意識の歯ぎしりは、自分では気づかないうちに歯に大きなダメージを与えていることが多いです。
- 過剰な力の影響: 特定の歯に負担がかかり、少しずつ前後・左右に動いてしまう。
- 噛み合わせの乱れ: 不均衡な圧力により、さらに歯の移動が進む。
- 歯ぐきや骨へのダメージ: 歯の根元に負担がかかり、歯周病の進行を助長。
このような歯のズレを防ぐには、ナイトガード(マウスピース)の使用が有効です。また、ストレスが原因で歯ぎしりをしている場合は、リラックス習慣を取り入れることも重要です。
片側噛みや頬杖などのクセが歯列に与える影響
日常の何気ないクセが、歯の位置をズレさせる原因になります。特に、片側だけで噛む習慣や頬杖をつくクセは、歯並びに大きな影響を与えます。
- 片側噛みの影響: 片側ばかり使うと、使わない側の歯が傾いたり、移動することがある。
- 噛み合わせのバランスの崩れ: 片側の歯がすり減り、顎の位置がズレる。
- 頬杖の影響: 顎に圧力がかかり、歯が押されて移動する。
このような習慣による歯の移動を防ぐには、左右均等に噛むことを意識し、座る姿勢を見直して頬杖をつくクセをやめることが重要です。
歯の喪失や矯正治療の影響で起こる歯の移動
歯が抜けたまま放置していると、周囲の歯が空いたスペースを埋めようとして移動し、歯並びがズレることがあります。
- 奥歯を失った場合: 隣の歯が傾いたり、噛み合う歯が伸びてしまう。
- 噛み合わせの崩れ: 他の歯にも影響を及ぼし、ズレが広がる。
- 虫歯・歯周病のリスク増加: 隙間ができて食べ物が詰まりやすくなる。
また、矯正治療後に適切な保定を行わないと、歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起こることがあります。これを防ぐには、リテーナー(保定装置)を適切に使用することが必要です。
ズレを防ぐためにできること
- ナイトガードを使用し、歯ぎしりの負担を軽減する。
- 左右均等に噛む習慣を身につける。
- 頬杖をつくクセをやめ、正しい姿勢を意識する。
- 歯を失った場合は早めに治療(ブリッジ・インプラント)を受ける。
- 矯正治療後は、歯科医の指示に従いリテーナーを使用する。
これらの対策を行うことで、歯のズレを防ぎ、長期間健康な歯並びを維持することができます。
早めの対処が大切!歯のズレを防ぐための予防策

噛み合わせを守るためのマウスピースの活用
歯のズレを防ぐためには、日常的にかかる噛み合わせの負担を減らすことが重要です。そのために有効な手段の一つが、マウスピースの活用です。マウスピースには、主に以下の2種類があります。
- ナイトガード(就寝時用): 歯ぎしりや食いしばりを防ぎ、歯への負担を軽減。
- スポーツ用マウスガード: スポーツ時の衝撃から歯を保護し、ズレを防ぐ。
ナイトガードのメリット:
- 寝ている間の無意識の歯ぎしりを防ぎ、歯のズレを予防。
- 顎関節症のリスクを減らし、顎の負担を軽減。
- 歯の摩耗を防ぎ、長期的に健康な歯並びを維持。
スポーツ用マウスガードのメリット:
- スポーツ時の衝撃による歯の転位や陥入を防ぐ。
- 歯の損傷や折れを防ぎ、長期的な健康をサポート。
歯科医院で適切なマウスピースを作成し、定期的にメンテナンスすることで、歯のズレを効果的に予防できます。
正しい姿勢や食生活で歯並びを整える
歯の位置は、顎の骨の成長や筋肉の使い方によっても影響を受けるため、日常的な姿勢や食生活を意識することで、歯並びの乱れを予防することができます。
正しい姿勢の重要性:
- 猫背になると頭部が前傾し、顎に余計な力がかかる。
- 長時間のスマホやPC作業で噛み合わせがズレやすくなる。
- 正しい姿勢を保ち、顎の位置を適切に維持することが大切。
食生活の改善ポイント:
- 硬い食べ物をよく噛むことで顎の筋肉を発達させる。
- やわらかい食品ばかり摂取すると、顎の成長が不十分になり歯のズレが進行する可能性がある。
- カルシウムやビタミンDを含む食品(乳製品、魚、ナッツ類)を摂取し、歯や顎の骨を強化する。
姿勢を意識し、バランスの良い食事を心がけることで、歯のズレを防ぎ、健康な噛み合わせを維持できます。
歯科医院で定期的な検診を受け、早期発見・早期治療を目指す
歯の位置のズレを防ぐためには、定期的な歯科検診を受け、歯並びや噛み合わせの状態をチェックすることが重要です。
歯科検診でチェックするポイント:
- 噛み合わせのズレが生じていないか。
- 歯の位置が正常な範囲にあるか。
- 歯ぎしりや食いしばりの影響で歯に負担がかかっていないか。
歯のズレが軽度の場合、噛み合わせの調整やマウスピースの使用で改善できることもあります。しかし、放置すると矯正治療や外科的処置が必要になる場合もあるため、早期発見・早期治療が重要です。
歯科医院で受けられる予防ケア:
- PMTC(プロフェッショナルクリーニング): 歯の汚れを徹底的に除去し、歯ぐきを健康に保つ。
- 噛み合わせの調整: ズレが進行しないように、歯科医が微調整を行う。
- 矯正相談: 歯のズレが進んでいる場合は、適切な矯正治療を検討。
定期検診の頻度は、最低でも半年に1回が推奨されますが、歯ぎしりや噛み合わせの問題がある場合は、3〜4ヶ月ごとにチェックを受けるとより安心です。
すでに歯がズレてしまった場合の治療方法

軽度の転位や陥入には矯正治療が有効
歯がズレてしまった場合、早期に適切な矯正治療を行うことで、元の位置に戻すことが可能です。特に、軽度の転位(歯の位置のズレ)や陥入(歯がめり込んだ状態)であれば、比較的短期間の矯正治療で改善が見込めることがあります。
矯正治療の選択肢:
- ワイヤー矯正(ブラケット矯正): 金属やセラミック製のブラケットを装着し、ワイヤーの力で歯を適切な位置に移動させる。中等度以上の転位や噛み合わせの問題に適用。
- マウスピース矯正(インビザラインなど): 透明なマウスピースを使用して歯を少しずつ動かす。軽度の転位や陥入に効果的。
- 部分矯正(MTM:Minor Tooth Movement): 特定の歯だけを矯正する方法。治療期間が短く、費用を抑えられる。
矯正治療の選択は、歯のズレの原因や状態によって異なるため、歯科医院での診断を受けて適切な方法を選ぶことが重要です。
噛み合わせの調整やクラウン・ブリッジによる補正
歯のズレが軽度で、矯正治療を行わなくても改善できる場合、噛み合わせの調整やクラウン・ブリッジによる補正が有効です。
噛み合わせの調整(咬合調整): 歯の高さや形を微調整し、噛み合わせを適切な状態にする。歯ぎしりや食いしばりによるズレを防ぐ。
クラウン(被せ物)による補正: 転位によって不揃いになった歯をクラウンで整える。歯を削る必要があるため、慎重な判断が必要。
ブリッジによる補正: 失った歯の周囲の歯が移動し、噛み合わせが乱れた場合にブリッジを使用。支えとなる歯を削るため、インプラントなどと比較しながら選択。
噛み合わせの調整や補綴治療は、短期間で改善できるメリットがありますが、根本的な噛み合わせの問題がある場合は矯正治療を併用することが推奨されます。
外科的処置が必要な場合の選択肢とリスク
歯の位置のズレが重度で、矯正治療や補綴治療だけでは改善が難しい場合には、外科的処置が選択されることもあります。
- 埋伏歯(顎の骨の中に埋まった歯)の牽引: 矯正装置を使用して歯を少しずつ引き出す治療。時間がかかるが、自然な歯を残せるメリットがある。
- 抜歯とインプラント治療: 重度の転位や矯正が困難な場合、抜歯後にインプラントを行い、適切な噛み合わせを確保。
- 顎の外科手術(オペラティブ矯正): 顎の骨自体に問題がある場合、矯正治療と手術を組み合わせて顎の位置を調整。顔全体のバランスも整える。
外科的処置は通常の矯正治療よりも負担が大きいため、メリットとデメリットを理解し、歯科医師と十分に相談することが重要です。
歯の位置のズレを放置した場合と治療を受けた場合の比較

歯並びが乱れたまま放置すると起こる将来的なリスク
歯の位置のズレを放置すると、見た目だけでなく、噛み合わせの悪化や口腔内の健康に深刻な影響を与えることがあります。
- 虫歯や歯周病のリスクが増加: 歯と歯の間に隙間ができたり、密集しすぎたりすることで歯磨きがしにくくなり、プラークや食べかすが溜まりやすくなる。
- 噛み合わせのバランスが崩れる: 奥歯の噛み合わせが悪くなると、前歯に負担がかかり、前方に押し出され「開咬(かいこう)」を引き起こす。
- 発音への影響: 歯の位置がズレると、「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になり、話す際に舌が歯に当たりやすくなる。
- 顔のバランスの乱れ: 片側の歯だけズレていると、そちら側の筋肉ばかりを使うため、左右のフェイスラインが非対称になり、顔のゆがみが目立つ。
- 顎関節症のリスク: 顎の位置がズレることで、関節や筋肉に負担がかかり、顎関節症の原因となる。
適切な治療を受けた場合の口腔内と顔のバランスの変化
歯の位置のズレに対する適切な治療を受けることで、口腔内の健康だけでなく、顔のバランスや咀嚼機能も改善されます。
- 噛み合わせの改善: 歯並びが整うことで噛む力が均等に分散され、顎関節への負担が軽減。
- 歯磨きのしやすさ向上: 矯正治療後は歯が適切な位置に並ぶため、ブラッシングがしやすくなり、虫歯・歯周病のリスクが低減。
- 顔のバランスが整う: 顎の位置が正常に戻り、左右対称のフェイスラインが形成され、若々しい印象を保つことができる。
- 発音が改善: 歯並びが整うことで、舌の動きがスムーズになり、発音のしやすさが向上。
- 消化機能の向上: 正しく噛めることで、食事の際の負担が軽減され、胃腸への負担が減る。
長期的な健康と見た目のために治療を選択する重要性
歯の位置のズレをそのままにしておくと、口腔内だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
- 消化不良の予防: 噛み合わせが改善されることで、食べ物をしっかり咀嚼できるようになり、消化器官への負担が軽減される。
- 肩こりや頭痛の軽減: 噛み合わせの悪化による顎の筋肉の緊張が解消され、首や肩への負担が減る。
- 第一印象の向上: 歯並びが美しく整うことで、清潔感があり、より自然な笑顔を作ることができる。
歯の位置のズレは、放置することでさまざまなリスクを引き起こしますが、適切な治療を受けることで、健康面・見た目の両方において大きな改善が期待できます。 矯正治療や噛み合わせの調整を行うことで、長期的に健康な歯を維持し、快適な生活を送ることができます。
歯のズレが気になるなら、まずは歯科医院で相談を!

歯並びや噛み合わせのチェックを受けるメリット
歯のズレが気になる場合、できるだけ早く歯科医院で噛み合わせや歯並びのチェックを受けることが重要です。自分では気づかないうちに問題が進行していることもあるため、専門的な診断を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。
歯科医院での噛み合わせチェックでは、以下のような点を確認します。
- 上下の歯が適切に噛み合っているか
- 特定の歯だけに過度な負担がかかっていないか
- 歯の傾きやねじれがないか
- 顎関節の動きに異常がないか
早期に対策を講じることで、治療期間を短縮し、最小限の介入で済むことが多くなります。例えば、軽度のズレであれば、部分矯正やマウスピース矯正で比較的短期間で改善できることがあります。
専門的な診断をもとに最適な治療法を提案
歯科医院では、レントゲンやCTスキャンを用いた精密検査を行い、歯のズレの状態や顎の位置を詳細に確認します。これにより、個々の患者に最適な治療プランを立てることができます。
歯のズレを改善する治療法には、以下のようなものがあります。
- 軽度のズレの場合: 噛み合わせの調整や部分矯正(歯を削って高さを調整、マウスピース矯正)
- 中等度のズレの場合: ワイヤー矯正やマウスピース矯正(インビザラインなど)
- 重度のズレの場合: 外科的処置を併用した矯正治療(埋まっている歯の牽引や顎の骨を調整する手術)
いずれの治療法を選択するにしても、歯科医師と相談しながら、自分のライフスタイルや治療の希望に合った方法を選ぶことが重要です。
健康な口元と美しい歯並びを維持するために、今できること
歯のズレを予防し、健康な口元を維持するためには、日常的なケアと歯科医院での定期的なチェックが欠かせません。以下の対策を実践することが大切です。
- 正しい噛み合わせを意識する: 片側ばかりで噛まないようにし、左右均等に噛む習慣をつける。
- 歯ぎしりや食いしばりを防ぐ: ナイトガード(マウスピース)を使用し、歯への負担を軽減。
- 定期的な歯科検診を受ける: 半年に1回のチェックで、歯並びの変化を早期発見。
- 矯正治療後の保定をしっかり行う: 矯正治療後はリテーナー(保定装置)を使用し、歯の位置を安定させる。
歯のズレは放置すると悪化しやすいため、気になる症状があれば早めに歯科医院で相談しましょう。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事