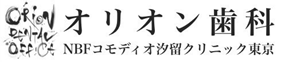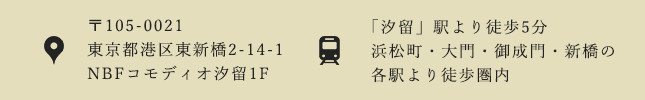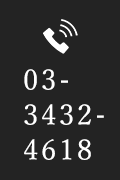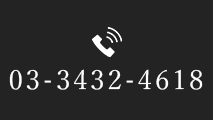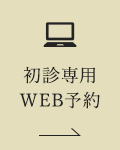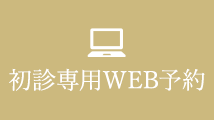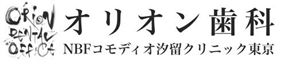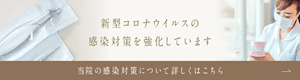大人の歯が抜けるのは加齢のせい?本当の原因とは

・歯周病が歯を失う最大の原因
歯を失う原因の中で最も多いのが歯周病です。歯周病は、歯を支えている骨(歯槽骨)を徐々に破壊していく慢性的な炎症性疾患で、痛みなどの自覚症状が出にくいため、気付かないうちに進行してしまうのが大きな特徴です。初期段階では、歯ぐきの腫れや出血、口臭といった軽微な変化しか現れませんが、進行することで歯を支える骨が溶かされ、歯がグラつき、最終的には自然に脱落してしまいます。特に40代以降の成人で歯を失う最大の原因とされており、「年齢だから歯が抜ける」と誤解している方も多いのですが、実際には歯周病の管理が不十分であることが大きな要因です。適切なブラッシングと、歯科医院での定期的なクリーニングとチェックを継続すれば、加齢に関係なく歯を一生保つことも十分可能です。歯ぐきの出血や腫れがある場合は、早期に受診することが重要です。
・虫歯の放置が抜歯につながるケース
虫歯も歯の喪失原因として見逃せません。特に虫歯を長期間放置した結果、歯の神経にまで感染が進んでしまうと、根管治療(歯の根の治療)が必要になります。さらに、根管治療を行っても炎症が治まらない、または歯根が破折している場合には、抜歯の判断が下されるケースもあります。虫歯が進行すると歯の構造そのものが脆くなり、かぶせ物の支えとなる土台が機能しなくなることもあり、これが抜歯に至る一因となります。また、再治療を繰り返すことで歯の耐久性が著しく低下し、保存が難しくなることもあります。重要なのは、虫歯の早期発見と初期治療です。小さな違和感や痛み、冷たいものがしみるといったサインを感じたときにすぐに対応すれば、多くの場合で歯を保存することが可能です。歯を守るには、予防と定期的なチェックが不可欠です。
・外傷や歯ぎしりによる脱落も無関係ではない
歯が抜ける原因は、病気だけではありません。外傷、すなわち転倒やスポーツ時の衝突、事故などによって歯が物理的に脱落するケースも多く見られます。特に前歯などは衝撃を受けやすく、完全に抜け落ちるだけでなく、根元で折れることもあります。また、長年の習慣による歯ぎしり(ブラキシズム)や食いしばりも、歯に大きな負担をかけています。強い力が継続的に加わることで、歯の表面が削れるだけでなく、歯の根に小さな亀裂が入り、結果的に歯根破折を起こして抜歯が必要になることもあります。これらは加齢とは無関係に起こるため、若年層でもリスクがある点に注意が必要です。就寝中の無意識な歯ぎしりに対しては、ナイトガード(就寝用マウスピース)の装着が推奨されます。歯を守るためには、日常生活での習慣や癖も見直し、必要に応じて歯科医師に相談することが大切です。
歯周病で歯を失うリスクとは?進行段階ごとの症状

・初期は自覚症状なし!出血や腫れに注意
歯周病は、初期段階ではほとんど痛みや目立った症状がないため、多くの人が気付かないまま放置してしまいます。最も初期の状態である「歯肉炎」は、歯と歯ぐきの間にプラーク(歯垢)がたまることで、歯ぐきに炎症を引き起こしている状態です。この段階では、歯磨きのときに出血したり、歯ぐきが腫れて赤くなるなどの症状が見られますが、痛みがないため軽視されがちです。しかし、歯肉炎を放置すると、炎症は歯を支える骨や歯根膜にまで広がり、「歯周炎」へと進行していきます。初期のうちに適切なケアを行えば、元の健康な状態に戻すことも可能ですが、見た目に異常がなくても症状が進んでいることがあるため、定期的な歯科検診でチェックすることがとても大切です。出血や腫れは小さな警告サインとして見逃さないようにしましょう。
・骨が溶け始めると歯がグラつく
歯周炎に進行すると、歯ぐきだけでなく、歯を支える骨(歯槽骨)が破壊され始めます。この段階では、歯ぐきが下がり始めて歯が長く見えるようになったり、冷たいものがしみたり、食べ物が詰まりやすくなったりするなど、日常生活で不便を感じるようになります。さらに進行すると、歯と歯ぐきの間の歯周ポケットが深くなり、細菌やプラークが溜まりやすくなる悪循環に陥ります。やがて歯の支持構造が著しく弱くなると、歯がグラグラと動くようになり、噛むと違和感や痛みを感じるようになります。これらの症状は「中等度から重度の歯周炎」に相当し、自然治癒することはありません。歯を支える骨が失われると、元の状態に戻すのは難しくなるため、ここまで進行する前に治療を始めることが重要です。歯が動くような感覚を覚えたら、すぐに専門的な診断を受けるべきです。
・歯の脱落につながる重度歯周病の危険性
重度の歯周病まで進行すると、歯を支える骨の大部分が破壊され、歯がしっかりと固定されなくなります。結果として、わずかな力で歯が動いたり、食事中に自然と歯が抜け落ちてしまうこともあります。この段階では、口臭が強くなったり、膿が出たり、歯ぐきが大きく腫れるなど、明らかな異常が見られます。また、歯周病菌が血流に乗って全身に影響を及ぼすこともあり、心臓病や糖尿病、誤嚥性肺炎など、さまざまな疾患との関連が報告されています。そのため、重度の歯周病は口腔内の問題にとどまらず、全身の健康にも悪影響を与える可能性があるのです。歯が抜けるまで放置してしまうと、入れ歯やインプラントといった補綴治療が必要になり、身体的にも経済的にも大きな負担がかかります。重症化を防ぐためには、初期段階での発見と予防、そして歯科医院での専門的な管理が欠かせません。
虫歯を放置すると歯を失う理由

・神経まで達すると歯の寿命が縮まる
虫歯は、歯の表面にあるエナメル質から始まり、象牙質、そしてその内部にある歯髄(神経)へと徐々に進行していきます。初期の虫歯であれば、削って詰め物をするだけで治療可能ですが、虫歯が神経にまで到達すると「歯髄炎」を引き起こし、強い痛みを伴うことが多くなります。この状態では、根管治療(いわゆる神経を取る処置)が必要となりますが、神経を抜いた歯は栄養供給を絶たれてもろくなり、時間の経過とともにひび割れや破折を起こしやすくなります。特に奥歯などは噛む力が強く加わるため、神経を失った歯にかかる負荷が大きく、結果として寿命が短くなる傾向があります。虫歯を放置し続ければするほど、治療は複雑化・大掛かりになり、歯の保存が難しくなっていくのです。違和感を感じた時点で受診することで、歯を長く残す可能性が高まります。
・根の感染が進むと抜歯が必要に
神経を取り除いた歯でも、根の中に細菌が残っていると再感染を起こすことがあります。この状態は「根尖性歯周炎」と呼ばれ、歯根の先に膿がたまり、腫れや痛み、噛んだときの違和感などを引き起こします。放置しておくと、感染が歯槽骨にまで広がり、周囲の骨を溶かしてしまいます。さらに悪化すると、顔の腫れや発熱を伴うこともあり、急性症状が現れることも少なくありません。根管治療によって再感染を防ぐことは可能ですが、根の形状や状態によっては治療が困難な場合もあり、そのようなケースでは歯の保存が難しく、抜歯という選択肢を迫られることになります。また、何度も再治療を繰り返している歯は、歯質の残りが少なくなっており、土台や被せ物を安定させることができず、結果として機能的に維持できないケースもあります。抜歯に至る前に、早めの治療が重要です。
・早期治療が歯を守る最大の鍵
虫歯による歯の喪失を防ぐうえで最も重要なのは「早期発見・早期治療」です。虫歯は自然に治ることはなく、放置すれば必ず悪化していく疾患です。初期段階では痛みがないため、「まだ大丈夫」「そのうち治るかも」と判断してしまう方も少なくありませんが、それは非常に危険な考え方です。実際、冷たいものがしみる、噛んだときに違和感があるといった小さな変化が、虫歯の進行のサインであることも多いのです。初期虫歯の段階であれば、削る範囲も小さく、歯へのダメージも最小限で済みます。しかし、神経や歯根に達するまで悪化してしまえば、保存が難しくなり、最終的には抜歯に至ることもあります。治療が早ければ早いほど、歯を残せる確率は高くなり、治療費や治療期間の負担も軽減されます。歯の寿命を延ばすためには、「痛くないから行かない」ではなく、「異変がなくても定期的に通う」意識が何より大切です。
歯が抜けたまま放置すると起きる問題

・噛み合わせの崩れが全体の歯に悪影響
歯は1本1本が独立しているように見えて、実は互いにバランスを取り合いながら並んでいます。そのため、1本でも歯が抜けると、その隣の歯が倒れてきたり、噛み合っていた反対側の歯が伸びてきたりと、全体の噛み合わせが崩れる可能性が高くなります。特に奥歯を失った場合、噛む力が前歯や他の歯に集中するようになり、それが他の歯への過剰な負担となり、次々と歯のトラブルを招く連鎖が始まってしまいます。こうした噛み合わせのズレは、単に歯の問題にとどまらず、顎関節症や頭痛、肩こり、姿勢の歪みなど、全身の不調につながるケースもあります。噛み合わせの微妙な変化は自覚しにくいため、歯が1本抜けた程度では「そのままでも問題ない」と感じるかもしれませんが、放置すればするほど修正が難しくなるため、早期の対処が重要です。
・顎の骨が痩せて老けた印象に
歯が抜けた状態を長期間放置すると、その部分の顎の骨(歯槽骨)が徐々に痩せてしまうという現象が起こります。これは、歯があった部分に噛む力がかからなくなることで、骨に対する刺激が失われ、「使われない部分が退化する」という自然な仕組みによるものです。特に前歯が失われた場合には、骨が痩せることによって唇や頬が内側に凹んでしまい、口元がしぼんだように見えることがあります。その結果、実年齢よりも老けた印象を与えてしまうのです。また、骨が痩せてしまうと、将来的にインプラント治療などを検討する際に骨造成(骨を再生する手術)が必要になる可能性もあり、治療がより複雑かつ高額になることもあります。見た目の若々しさを保つためにも、歯を失った後の速やかな処置が重要です。
・食事・発音・見た目…生活の質が低下
歯を失うことで最も日常生活に影響が出るのが「噛む・話す・見た目」という基本的な機能です。まず、噛む力が低下することで、食事にストレスを感じるようになり、食べ物の制限が出てきます。硬いものが噛みにくくなると、栄養バランスが偏る恐れがあり、健康全体に悪影響を及ぼします。特に高齢者にとっては、噛めないことで食事量が減り、体力や免疫力の低下を招く危険性もあります。また、歯が抜けたことで発音が不明瞭になるケースもあり、会話にコンプレックスを感じたり、外出や人前で話すことを避けてしまう方もいます。見た目に関しても、前歯がない状態は笑ったときに目立ちやすく、口元への自信喪失が心理的なストレスを引き起こすことがあります。つまり、1本の歯を失うだけで、食事・会話・見た目という生活の質の三本柱が揺らぎ、心身の健康に大きな影響を及ぼすことがあるのです。
ブリッジ治療のメリットと注意点

・健康な歯を支えにする仕組み
ブリッジ治療とは、歯が抜けた部分の両隣の歯を支えにして人工歯を装着する治療方法です。構造としては、橋(bridge)のように両側の健康な歯を土台(支台歯)として、間の歯を補う形で被せ物を作製します。1本だけ歯が抜けた場合など、支えとなる隣の歯が健在であることが前提となります。治療の際には、支台歯を削り、型取りをして、数週間後にブリッジが完成し装着するという流れになります。インプラントのように外科手術が必要ないため、比較的短期間で見た目と機能の回復が図れるのが特徴です。また、材料としては保険診療で使える硬質レジン前装冠から、自費診療で選べるセラミックやジルコニアまで選択肢があり、審美性や耐久性のバランスを考えて治療を進められる点も、患者様にとってメリットの一つです。
・短期間で機能回復できる利点
ブリッジは、入れ歯やインプラントと比較して、比較的早く噛む力を回復できる治療法として広く知られています。治療期間は個人差がありますが、概ね2〜4週間程度で完了することが多く、外科手術の回復期間が必要なインプラント治療と比べても、身体的な負担が少ないのが特徴です。さらに、入れ歯のように取り外しをする必要がなく、固定式であるため装着後の違和感が少なく、口の中で安定した噛み心地を得られるのも大きな利点です。また、素材によっては天然歯とほとんど見分けがつかないほど自然な仕上がりにできるため、審美的な満足度も高い傾向にあります。食事や会話も治療前と変わらない感覚で行えることから、仕事や日常生活への復帰が早いという点でも患者様の支持を集めています。 しかし、これらの利点を享受するためには、支台歯の健康状態や咬み合わせのバランスが良好であることが前提となるため、事前の診断が非常に重要です。
・支台歯への負担と削るデメリット
ブリッジ治療の大きなデメリットとして挙げられるのが、健康な歯を大きく削る必要があるという点です。支台歯として選ばれた両隣の歯は、たとえ虫歯や詰め物がなくても、被せ物を装着するためにある程度の量を削る必要があります。これにより、支台歯の寿命を縮めてしまう可能性があるのです。また、削られた歯に神経が残っている場合、将来的に知覚過敏や痛みが出るリスクも伴います。さらに、ブリッジ全体で噛む力を支える構造上、支台歯に大きな咬合力(噛む力)がかかり続けるため、長期的には支台歯が破折や歯周病によりトラブルを起こすこともあります。 特に、ブリッジの下の部分(ダミー部分)は清掃しにくく、プラークや食べかすが溜まりやすいため、口腔内の清潔を保つために特別なケアが必要です。フロスや歯間ブラシの使い方を歯科医師や衛生士から正しく学び、日常的にケアを続けることが、ブリッジを長持ちさせる秘訣です。手軽な治療法に見えるブリッジですが、支台歯への影響をよく理解したうえで選択することが大切です。
入れ歯の種類と適応ケース

・部分入れ歯と総入れ歯の違い
入れ歯には大きく分けて「部分入れ歯」と「総入れ歯」があります。部分入れ歯は、自分の歯が一部残っている場合に用いられ、金属のバネやアタッチメントを利用して残存歯に固定するタイプです。一方、総入れ歯は上下いずれか、あるいは両方の歯をすべて失った際に使用され、歯ぐき全体を覆うような形で装着されます。部分入れ歯は比較的安定しやすく、装着感も良好ですが、残っている歯の状態によってはバネのかかり具合や強度に影響が出ることもあります。総入れ歯は土台となる歯がないため、歯ぐきや顎の形状にしっかりと合うように精密な調整が必要で、装着直後は違和感や痛みを感じやすい場合もあります。また、どちらのタイプも取り外し可能であるため、清掃しやすい反面、外れやすい、噛みにくいといった悩みを抱える方も少なくありません。このように、入れ歯はその種類によって適応条件や使用感が異なるため、事前の十分な説明と相談が必要です。
・保険・自費による機能性と審美性の差
入れ歯には保険診療の範囲で作成できるものと、自費診療で作成する高機能・高審美タイプがあります。保険の入れ歯は、レジン(樹脂)製の床が標準で、比較的費用が安く、広く普及していますが、厚みがあるため装着感に違和感を覚える方も少なくありません。また、部分入れ歯の場合は金属製のバネが目立ちやすく、見た目の点で気になる方には不向きな場合もあります。一方、自費の入れ歯では、金属床を用いた薄くて丈夫な設計や、ノンクラスプデンチャーと呼ばれる金属バネのない審美的なタイプも選べます。これにより、より自然な見た目と快適な装着感を得ることが可能です。また、自費の入れ歯は設計の自由度が高く、患者様一人ひとりの噛み合わせや口腔内の状態に合わせたオーダーメイド設計ができるため、機能性にも優れています。ただし、費用が高くなるため、予算や使用目的に合わせた選択が求められます。
・適合性と装着感を保つための工夫
入れ歯は一度作って終わりではありません。使用しているうちに顎の骨が痩せたり、歯ぐきの形が変わったりすることで、装着時のフィット感が徐々に悪くなることがあります。そのため、定期的な調整やメンテナンスが必要不可欠です。特に総入れ歯の場合、噛む力の負荷が直接歯ぐきにかかるため、痛みや不快感が出やすい傾向にあります。これを防ぐために、入れ歯の裏側に「裏打ち(リライニング)」と呼ばれる調整を施すことがあります。また、日常的に入れ歯を清潔に保つことも重要です。入れ歯専用のブラシや洗浄剤を使用し、食べかすや細菌の付着を防ぐことで、口臭や炎症のリスクを低減できます。さらに、入れ歯を使いこなすためには、最初の装着時に無理せず、少しずつ慣れていくことも大切です。歯科医師と相談しながら調整を繰り返すことで、自分の口にフィットする入れ歯へと仕上げていくことができます。
インプラントで失った歯を取り戻す

・骨と結合する構造で天然歯のように噛める
インプラントとは、失った歯の代わりに人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。最大の特徴は、インプラント体が顎の骨としっかり結合すること(オッセオインテグレーション)。これにより、まるで天然の歯が生えているかのような安定性と噛み心地を実現できます。部分入れ歯のようにズレたり外れたりする心配がなく、硬い食べ物もしっかり噛めるため、食事のストレスを大きく軽減することが可能です。また、インプラントは隣の歯を支えにするブリッジと違い、他の健康な歯に負担をかけることがありません。そのため、長期的に見ても他の歯の寿命を保ちやすく、口腔内の全体的な健康を維持しやすい治療法といえます。さらに、審美性にも優れ、見た目も非常に自然な仕上がりになるため、前歯など見た目を重視する部位にも適しています。
・他の歯に負担をかけない独立型の補綴
インプラントが「第3の永久歯」とも呼ばれる理由のひとつは、周囲の歯に一切の負担をかけずに独立して機能する補綴物であることです。ブリッジ治療では、失った歯の両隣の健康な歯を大きく削って支台とする必要があり、その歯に強い咬合力が加わり続けることで、将来的に支台歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。入れ歯も、バネを引っ掛ける残存歯に力が加わるため、長期的には歯周病や動揺を引き起こすことがあります。一方、インプラントは人工歯根が骨と結合するため、自立してしっかりと噛む力を支えることができるのです。この“独立性”が、インプラントの大きな魅力であり、他の補綴治療と比較して周囲の天然歯を守る力が強いとされています。また、1本単位での治療が可能なため、必要な部分だけに最小限の介入で済むのもメリットです。口腔全体のバランスを崩さず、他の歯の健康を保ちながら欠損部を補いたい方にとって、非常に理にかなった治療といえるでしょう。
・手術が必要な点と成功のための条件
インプラント治療は大きなメリットを持つ一方で、外科手術を伴うため、誰にでも適応できるわけではありません。治療ではまずCTなどによる精密検査を行い、顎の骨の厚みや質、全身の健康状態などを総合的に評価します。糖尿病や高血圧などの持病がある方、喫煙習慣がある方は治療後の回復に影響が出る可能性があるため、慎重な診断とリスク管理が求められます。また、歯周病がある状態でインプラントを埋入すると、インプラント周囲炎というトラブルのリスクが高まり、インプラントが抜け落ちてしまう可能性もあるため、事前の口腔内環境の整備が不可欠です。さらに、インプラントが骨と結合するまでには数ヶ月の治癒期間が必要で、その間は定期的な診察と適切なセルフケアが求められます。成功率は非常に高い治療法ですが、「治療を受ければ終わり」ではなく、治療後のメンテナンスが長期的な成功の鍵となります。インプラントを安全かつ長持ちさせるには、経験と実績のある歯科医院を選ぶことが重要です。
治療法の選び方はどう決める?比較ポイント

・歯の位置・本数・骨の状態が判断材料
歯を失ったときの治療方法は、「どの治療が良いか」ではなく、「どの治療が自分に合っているか」を考えることが大切です。まず大きな判断基準となるのが、歯を失った位置と本数、そして顎の骨の状態です。例えば、奥歯の欠損で周囲の歯が健康であれば、インプラントが適しているケースが多いです。一方、複数本連続して歯が抜けている場合には、ブリッジや部分入れ歯の選択肢が現実的となることもあります。また、インプラントは顎の骨がしっかりしていることが前提条件のため、骨の厚みや密度が不足している場合には、骨造成などの追加処置が必要になることもあります。さらに、残っている歯の状態も重要で、虫歯や歯周病がある場合には、それらを先に治療してから補綴を考える必要があります。口腔内の全体バランスを見ながら、適応できる治療法を専門的な視点で見極めることが求められます。
・見た目・噛み心地・手入れのしやすさで選ぶ
補綴治療の選択には、「機能性」と「審美性」、そして「メンテナンス性」という3つの視点が欠かせません。見た目を重視するならば、インプラントやセラミックを使用したブリッジが自然な見た目に仕上がりやすく、前歯など審美性が求められる部位に適しています。噛み心地については、インプラントが最も天然歯に近い感覚を再現できるため、硬いものでもしっかり噛める点が魅力です。一方で、入れ歯は取り外し式であるため、違和感を感じやすかったり、食べ物の選択肢が限られることもあります。また、日々の手入れという観点では、固定式のブリッジやインプラントは見た目が良く快適ですが、歯間や人工歯の下に汚れがたまりやすく、専用のケアが必要になります。入れ歯は取り外しができる分、清掃はしやすい反面、外したり装着したりする手間や、使用中の安定感に不安が残ることも。このように、それぞれの治療法には利点と欠点があるため、日常生活でどこに重点を置くかが選択の鍵となります。
・費用とライフスタイルも要素の一つ
治療法の選択において、現実的に大きな要素となるのが「費用面」です。保険適用のブリッジや入れ歯であれば、比較的安価に治療を受けられる一方、インプラントや自費の入れ歯・ブリッジは高額な費用がかかる場合があります。ただし、高価な治療が必ずしも「贅沢」なわけではありません。例えば、インプラントは初期費用が高くても、長期的には再治療のリスクが低く、トータルコストが抑えられる可能性もあるのです。また、通院回数や治療期間も重要なポイントです。仕事が忙しくて頻繁に通院できない人にとっては、短期間で完了できるブリッジが現実的な選択肢になることも。さらに、年齢や生活スタイルも考慮すべきです。高齢者であれば、手術が必要なインプラントよりも、身体への負担が少ない入れ歯を優先するという判断も理にかなっています。このように、単に「何が良いか」ではなく、自分のライフスタイルにとって無理のない選択をすることが、満足度の高い治療につながります。
歯を失わないための予防習慣

・正しいブラッシングと補助清掃の徹底
歯を長く健康に保つためには、日々のセルフケアが何より重要です。中でも、基本となるのが「正しい歯磨き」。ただし、単に磨いているだけでは不十分で、磨き残しの多い場所や、強すぎるブラッシングによる歯ぐきの損傷など、自己流の磨き方では歯を守ることができないこともあります。特に歯と歯ぐきの境目、奥歯の裏、歯並びが悪い箇所はプラークが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯ブラシは「やわらかめ」を選び、毛先が広がっていないものを使用しましょう。また、毎食後のブラッシングが理想ですが、少なくとも朝と夜の2回は丁寧に時間をかけて磨く習慣が大切です。さらに、歯ブラシだけでは落としきれない歯間の汚れを除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシを毎日使うことを習慣化することが、歯の寿命を延ばす大きなカギとなります。
・食習慣や生活リズムの見直しも重要
歯を守るためには、口腔ケアだけでなく、日々の食生活や生活習慣も大きく関わっています。まず、糖質の摂り過ぎは虫歯の原因菌が酸を産生しやすくなるため、間食や甘い飲み物の頻度には注意が必要です。特に、砂糖入りのコーヒーやジュースをちびちび飲む習慣は、口の中を酸性に保つ時間が長くなり、歯の表面(エナメル質)を徐々に溶かしてしまうリスクが高くなります。また、睡眠不足や過度なストレスは、免疫力を低下させ、歯周病菌への抵抗力を弱めることが分かっています。さらに、ストレスによって無意識に歯ぎしりや食いしばりをしてしまう人も多く、歯に強い力がかかることで、ひび割れや歯根破折の原因にもなり得ます。食事はバランスよく、よく噛むことで唾液の分泌を促し、口腔内の自浄作用を高めることも重要です。歯の健康を守るためには、日々の生活習慣全体を見直す視点が欠かせません。
・定期検診で異変を早期に察知
どれだけ丁寧にセルフケアをしていても、100%完璧に歯を守ることはできません。自分では気づかないうちに虫歯ができていたり、歯ぐきの中で歯周病が静かに進行していることもあるため、定期的に歯科医院でチェックを受けることが不可欠です。定期検診では、歯や歯ぐきの状態をプロの目で確認し、小さな異変も見逃さず早期に対処できます。初期の虫歯や歯周病は痛みがないことがほとんどですが、早めに見つければ削らずに済むこともあり、将来的な歯の寿命を延ばすことにもつながります。また、歯石や着色など、家庭でのケアでは落とせない汚れを落とす「プロフェッショナルクリーニング(PMTC)」も、予防効果を高める重要なケアです。通院の目安としては、3~6ヶ月に1回が一般的ですが、歯周病のリスクが高い方は、より短い間隔でのチェックをおすすめします。歯を失わないためには、セルフケアとプロケアの“両輪”が必要不可欠です。
歯を守るために、今できる最初の一歩

・グラつきや違和感は早期受診のサイン
「最近歯が揺れるような気がする」「噛んだときに軽い痛みがある」など、口の中で感じるちょっとした違和感。それは、歯の健康が崩れ始めているサインかもしれません。歯周病の初期や歯の根のトラブル、歯ぎしりによる過剰な力の蓄積など、グラつきの原因はさまざまですが、放置すれば進行し、最終的に歯を失うリスクが高まります。また、冷たいものがしみる、噛むと響くといった症状も、神経に近い部分の虫歯や咬合性外傷(噛み合わせによるダメージ)が原因となっている場合があり、早期の処置が必要です。自己判断で様子を見るのではなく、違和感を感じた時点で歯科医院を受診することが、歯を守るための第一歩です。早期発見・早期治療ができれば、歯を削る量も最小限で済み、治療期間や費用も抑えられる可能性が高くなります。何も問題がないと思っていても、違和感を見過ごさない感覚が、将来の歯の寿命を大きく左右するのです。
・適切な治療計画で未来の歯を守る
歯のトラブルが起きた際、「とりあえず治す」ことに終始してしまいがちですが、本当に大切なのは、目の前の問題だけでなく“将来”を見据えた治療を行うことです。例えば1本歯を失ったとき、ブリッジにするのか、インプラントにするのか、入れ歯にするのかで、残っている他の歯や顎の骨への影響が大きく変わってきます。短期的に手軽な治療を選んでも、長期的には支台歯がダメージを受けてさらに歯を失ってしまうこともあるのです。そのため、患者様一人ひとりの口腔内の状態や生活スタイル、年齢などを考慮した中長期的な視点の治療計画が必要不可欠です。信頼できる歯科医院では、現在の状態の説明だけでなく、将来的なリスクや治療の選択肢についても丁寧に説明してくれます。必要に応じてCT撮影や噛み合わせの検査などを行い、精密な診断をもとに、最も適した治療法を選択することが歯を長く保つための鍵となります。
・信頼できる歯科医院で安心の治療選びを
歯を守るためには、セルフケアの努力だけでなく、質の高い治療とメンテナンスを受ける環境を整えることも重要です。そのためには、信頼できる歯科医院との出会いが欠かせません。信頼できる歯科医院とは、単に設備が整っているというだけでなく、患者とのコミュニケーションを重視し、疑問や不安に丁寧に対応してくれる場所です。初診時のカウンセリングでどれだけ丁寧に話を聞いてくれるか、治療方針をきちんと説明してくれるかを見極めることが大切です。また、歯科医院選びでは、予防歯科に力を入れているか、定期検診の体制が整っているかも大きなポイントです。治療だけでなく、歯を失わないための習慣づくりをサポートしてくれる存在こそが、あなたの歯の健康を長期にわたって守ってくれるパートナーになるはずです。「何かあってから通う歯医者」ではなく、「何も起こらないように通う歯医者」を選ぶことが、結果的に自分の歯を守る最良の方法となります。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事